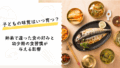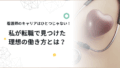子どもが友達の家に遊びに行くのはいつからがいい?
「友達の家に遊びに行っていい?」
子どもからそう聞かれたとき、皆さんはどう答えますか?
小学校に入学すると、友達との関わりがぐっと増えてきます。自然と「家に遊びに行く・来てもらう」という機会も増えていきますよね。楽しい時間を過ごしてほしい一方で、まだまだ小さな子ども同士です。安全に遊べるか、トラブルが起きたときにどう対応するか、相手のご家庭との関係性はどうか、考えることがたくさんあります。
私自身、子育てをしながら「友達の家に遊びに行くのはいつから?どんな基準で許可する?」と度々考えることがありました。特に、我が家では長女が小学校1年生のときに友達の家でトラブルがあった経験から、このテーマに慎重になりました。
今回は、子どもが友達の家に遊びに行くタイミングと、我が家で決めているルール・基準についてご紹介します。実体験をもとにしたエピソードも交えながら、同じように悩む方の参考になれば嬉しいです。

小学1年生の長女に起きたトラブルから学んだこと
最初にお友達の家に遊びに行ったのは長女が小学校1年生のときでした。
何度か誘われていたのですが、まだ送り出すのが心配でお断りしていました。「他のお友達は何度も遊びに行っているよ」という長女の言葉と、何度もお断りするのは申し訳ない気持ちがあり、「そろそろ大丈夫かな」と送り出したのですが──
後から子ども同士のけんかがあったことを知り、驚きました。
しかも、そのお家のご両親とはまだ知り合ったばかりで、お互いに気軽に連絡できるような関係ではなかったため、詳しい状況の確認やその後のフォローが難しく、もどかしい思いをしました。
この経験を通して、「信頼関係のないまま子どもを送り出すのはリスクがある」と強く感じました。
保健師として考える「遊びに行く前に育てたい力」
子ども同士の遊びは、社会性や想像力、協調性を育む大切な時間です。しかしその一方で、親の目の届かない場所で過ごす以上、「安心・安全に遊べる力」が大切になります。
保健師として子どもの育ちを見ていると、あいさつ、靴をそろえる、遊んだものを片付ける、危ないことを避けるなど、基本的なマナーや生活習慣は、小さな積み重ねから身についていきます。「家庭外の人と関わる力」は、急に育つものではありません。
我が家でも、そうした力がある程度身についているかを見て、遊びに行かせるようにしています。それは、子ども自身の自立のためでもあり、相手のご家庭への配慮でもあります。遊びに行かせることは、子どもへの信頼と責任を持たせる機会にもなるのです。
我が家の基本ルール:「いつから」より「どんな準備ができているか」
子どもが何歳だからOK、というよりも、「どんなふうに人の家で過ごせるか」が大切だと考えています。
我が家では、以下のようなマナーができていることを一つの目安にしています。
✅ 1. あいさつがきちんとできる
玄関で「こんにちは」、帰るときは「ありがとうございました」。
基本のあいさつが自然にできることは、最低限のマナーとして見ています。
普段の生活から心がけたいことですよね。
✅ 2. くつをそろえる
些細なことのようですが、第一印象はここで決まることも多いです。
「おじゃまする」という気持ちが行動に出る部分なので、普段から練習しておきたいポイントです。
✅ 3. 遊んだおもちゃを片付ける
遊びっぱなしで帰るのではなく、「遊ばせてもらった」ことに感謝を込めて、片付ける姿勢が大切です。

相手のご家庭との関係性も大切
マナーができていても、子ども同士だけでやりとりするのはまだ早いと感じることもあります。約束の日時が曖昧で、「本当に相手のお家の方は知ってるの?」と心配することも多々あります。
我が家では、長女の時の経験から、以下のようなことを確認しています。
- 保護者と顔見知りであること
- 連絡先を交換していること
- 「何時までに帰るか」などを親同士で共有できる関係であること
このように、親同士が連絡を取り合える関係があると、お互いに「もし何かあったらすぐ連絡できる」と安心感が大きく違います。
長男は“活発すぎて心配”だった
長男は長女に比べて外遊びが大好きで、友達との関わりも活発です。
そのため、遊び中のケガも心配ですし、「何か壊してしまったら…」という不安もありました。
そのため、友達の家に遊びに行く年齢も、長女より遅くなりました。
当然ながら、本人は「なんでお姉ちゃんはいいのに僕はだめなの?」と不満そうでした。
でも、私は「安全に遊べるようになること、きちんとあいさつや片付けができるようになったら行こうね、相手の家の人にも安心してもらえるからね」と伝えました。

はやく許可をもらいたい長男は、玄関で靴をそろえるようになり、遊びに夢中になりすぎた時も、その話を思い出させると、はっとしたように注意するようになりました。
子どもなりに「信頼される行動」を考えるようになったのだと思います。
最初は短時間&送迎。不安なときは「うちにおいで」から始める
初めての場合は、時間を決めて短めにしています。
また、送迎はできるだけ親が行い、相手の保護者に一言ご挨拶するようにしています。
「まだちょっと心配…」という場合は、お友達を自宅に招くことからスタートしても良いと思います。我が家も、初めて遊ぶお友達は、まずは「うちにおいで」から始めます。
子どもの関わり方やルールの理解度も見えてきます。
まとめ:年齢よりも「準備」が大事。親も子も成長できる経験に
友達の家に遊びに行くのは、親子にとってもひとつの「成長のステップ」です。
トラブルを経験したからこそ、準備と信頼の大切さに気づけました。
そして、きちんと伝えれば、子どもも自分なりに意識して行動するようになるものです。
焦らず、少しずつ、子どもの繋がり、社会を広げていけるといいですね。