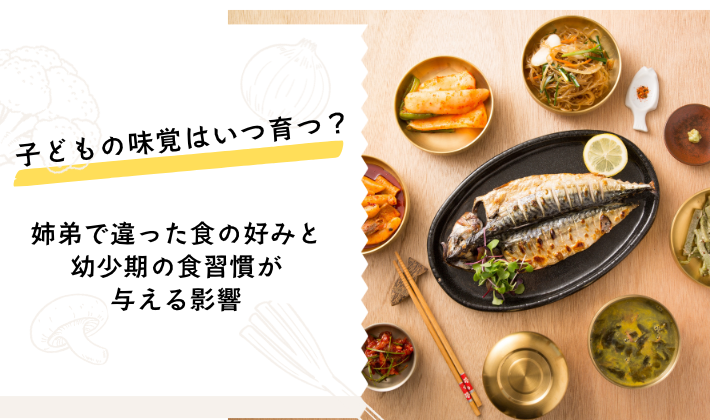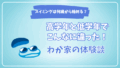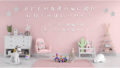はじめに:子どもの食の好みはどう育つ?
同じ家庭で育っても、子どもの「食の好み」は驚くほど違うことがあります。わが家には小学生の姉弟がいますが、食欲旺盛な2人にもかかわらず、好みが大きく異なります。特におやつの選び方には差があり、その背景には幼少期の食習慣が関係しているのではと感じています。今回は、姉弟それぞれの嗜好や育て方を振り返りながら、味覚の育ち方や健康への影響について考えてみたいと思います。

子どもによって異なる味の好みと健康への影響
長女はジュースや炭酸飲料が苦手で、スナック菓子も「味が濃い…」と言って進んで食べません。ファミリーレストランに行っても、ドリンクバーではウーロン茶を選びます。一方で長男はスナック菓子やジュースが大好きで、濃い味付けの料理も平気で食べます。
2人とも標準的な体型で大きな健康問題はありませんが、長女は虫歯が一度もないのに対して、長男はすでに何度か治療経験があります。この違いは、日々の食習慣、特に間食や飲料の選び方が影響していると感じています。

長女は理想的な食習慣からスタート
教科書通りの離乳食と手作り中心の幼少期
長女は初めての育児ということもあり、教科書通りの理想とされる離乳食を実践していました。市販のお菓子やジュースは3歳まで控え、お出かけの時も外食も避けて手作りのお弁当を持参する生活でした。おかげで、薄味を好み、お菓子の味を知らないまま成長し、欲しがることもなく自然と健康的な嗜好に育ちました。
長男は“見て覚える”弟ならではの環境
姉の影響と周囲の環境がスタートを変えた
2歳下の弟は、姉がすでに色々なものを食べる姿を見て育ちました。そのため、ジュースやスナック菓子にも早くから興味を持ち、自然とデビューも早まりました。周囲から長女と同じように与えられるため、制限するのが難しかったという背景もあります。
このように、幼少期の食環境の違いが、味覚や嗜好に影響している可能性は大いにあると実感しています。
大切なのは「知って選ぶこと」
今のところ、虫歯以外の健康面の違いはありませんが、肥満や病気の予防を考えると、弟の希望通りの食生活というわけにはいかず、結果として弟はガマンが大きく、姉の方がストレスの少ない食生活になっています。
長女の育て方が必ずしも正解とは限りません。むしろ、過剰に制限することで親のストレスになったり、家庭の雰囲気が悪くなるようでは本末転倒です。ただ、選択の幅を広げるためにも「知っていること」は大きな力になります。
市販のおやつが必ずしも悪ではありませんが、影響や選び方を知っていれば、より子どもに合った方法を取れるのではないでしょうか。
保健師として伝えたいこと 〜食の習慣は未来への投資〜
私は普段、保健師として妊婦さんや乳幼児のママたち、大人の生活習慣病予防、高齢者の健康支援など、あらゆる世代の方と関わる機会があります。その中で共通して感じるのは、「幼少期の生活習慣がその後の人生に与える影響は本当に大きい」ということです。
とくに食習慣は“気づいたとき”からでも整えられるものではありますが、「最初にどう身につけたか」によってその後の選択に大きく関わってきます。たとえば、お菓子の味に慣れてしまった子どもが、野菜や素材の味をおいしく感じるまでには、時間と工夫が必要です。
支援の現場でも、
「知っていれば、もっと早く気をつけられたのに」
「身体に良くないと分かっていても、子どもが欲しがるとつい…」
という声を多く聞いてきました。
だからこそ私は、“選択肢を知って、自分たちに合ったやり方を選べる”サポートが大切だと思っています。

食習慣は一生に関わること。だからこそ、できる範囲で、子どもの未来につながる選択をサポートしていきたいと思っています。そして、子ども自身にも「自分の健康は自分でつくれる」という意識を持ってもらいたいと願っています。
今回の記事も、ひとつの事例として読んでくださった方の「気づき」につながれば嬉しいです。完璧じゃなくていい、でも“知っていることでできること”は確実に増える。長男に対して「もっと気を付けてあげられたら」と思うこともありますが、まだ遅くはありません。そう思いながら、これからもわが家の食生活を見直していきたいと思っています。