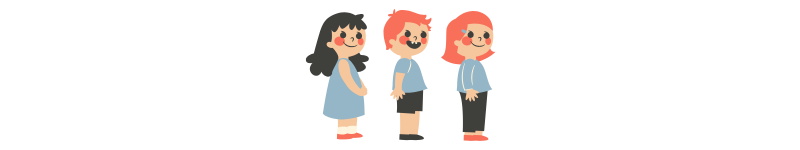子どもの体は、食べたものでつくられる
育ち盛りの子どもたち。私は公務員からフリーランスに転身してからも、食費だけは多少かかっても、体に良い食材を選ぶようにしています。
食べたもので子どもの体はつくられます。それだけでなく、集中力や感情の安定など、心の健康にも食事は深く関わっています。
保健師としても、日々の食事の積み重ねが子どもの一生の健康習慣につながることを強く実感しています。だからこそ「何を選ぶか」は、子どもの未来を左右する大切な行動のひとつだと思っています。
食べさせたいもの vs 子どもが食べたいもの
…とはいえ、体に良いものほど子どもには不人気、というのが現実です。ファーストフードや濃い味のおかずが好きで、野菜や玄米はなかなか進まない…。
うちの場合、長女(小6)は美容への関心が出てきたので「これ食べるとお肌つるつるになるよ」といった説明が効果的。一方、長男(小4)は「今食べたいもの」がすべてなので、なかなか理屈では響きません。

喜ぶメニューを、できるだけヘルシーに
だから私は「好きなメニューの中で、できるだけ体に良い食材に置き換える」ようにしています。たとえば、大豆ミートのハンバーグやミートソースは、見た目も味もほとんど変わらず喜んで食べてくれます。
ヨーグルトやサラダにはアマニ油を、牛乳の代わりに豆乳や低脂肪乳を。手の込んだ料理はできなくても、選ぶものを変えるだけでも十分なんです。
習慣化には「続ける」ことが一番のコツ
保健師としての経験からも、「子どもの食習慣は、親の食卓から始まる」とよく感じます。はじめは嫌がられても、繰り返すうちに自然と慣れてきます。
うちでは玄米や雑穀米を毎食出すようにしています。以前は「白いご飯がいい!」と文句を言っていましたが、「元気に学校へ行くためだよ」「マラソン大会で勝ちたいなら、こっちのご飯がいいよ」と伝え続けた結果、今では「うちはこれが普通」と言ってくれるように。
「納得した」というよりは「諦めた」のかもしれませんが(笑)、それもひとつの進歩です。

保健師として伝えたい「完璧じゃなくていい」食事の話
子どもにとっても親にとっても、「食」は毎日のこと。だから私は「100点を目指さなくてもいい」と思っています。完璧を求めると続きませんし、無理をするとストレスになります。
ジャンクフードの日もあっていいし、「今日はもういいや」と手を抜く日も必要。その代わり、「意識して少しでもバランスを整える」ことが続けるコツです。
保健師としての立場からも、家庭の健康づくりに必要なのは“完璧な栄養管理”ではなく、“無理のない継続”です。
まとめ:子どもの未来は、日々の選択の積み重ね
今は「食べたがるもの」をすべて与えるのではなく、「将来にわたって元気に生きていける食習慣」を育てる時期。親が選ぶもの、出すものが、子どもの「当たり前」になっていきます。
毎日の食事でできることを少しずつ、無理せずに取り入れていく。それだけで、子どもの体と心はきっと育っていきます。